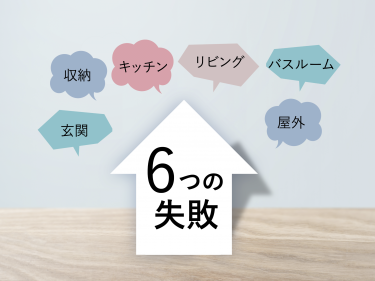換気性能を上げるためにはC値を意識


大森さん
最後は「換気性能」ですね。僕だけじゃなくて、今の子育て世代の方々は共働きされてる方が多くて、室内干しをされる方も多くなりました

初谷
確かに、取材をしていると共働きの方や室内干しをされている方は多いですね

大森さん
やっぱりそうですね。室内干しした時に、生乾きとか変な匂いがするっていうのは、やっぱりストレスになりますので、その時に換気性能と、プラスアルファで言ったら、気密性能を担保できると、びっくりするぐらい気持ちよく乾きます。これも残念ながら僕は体感できてなくて、オーナー様からそういうお喜びの声をいただいています

初谷
換気性能っていうのは、どういうところで上げることが出来るんですか

大森さん
建築基準法で24時間換気っていうのが、義務付けられています。簡単に言えば、家中の全てのドアと窓を閉めている状態で、2時間に1回、外の空気と中の空気は入れ替わるっていうのが換気性能で、計画換気と言われるものです。でも、計画通りに空気が動いてないことも多いんです

初谷
機能を備えていればよいということではないんですね

大森さん
はい。換気計算をするときには、気密性能は加味しないんです。つまり、家中の隙間は0という前提で換気計算はされているんですよ

初谷
気密の概念を入れてないんですね

大森さん
要素を入れ出したらキリがないっていう考えなのかもしれませんね。気密性能が良かったら、ロジックとしては、空気がしっかり動く。分かりやすく言ったら、例えばアイスコーヒーをストローで飲むとき、当然ですが吸ったら飲めますよね。でも、そのストローに、穴を空けると吸えなくなるんですよ

初谷
その例はすごく分かりやすいです


大森さん
気密性能がゼロではないから、空気が計画通り動いてないっていうことですね。そしたら、空気が動かないので、そこに洗濯物を干しても、乾きにくい

初谷
なるほど。気密性能を考えながら、換気性能を上げる必要があるということですね

大森さん
そうです。家の中で空気が動くと、気持ちもいいですね。1日中、家の中にいても不快じゃありません。その点で僕の家は長くはいられないし、洗濯物が乾かなくてエアコンもガンガンにかけないといけません

初谷
そうなんですね。性能の良し悪しは、施工会社によって大きく変わるものなんですか?

大森さん
これは残念ながら大きく変わりますね。ここまでにしないといけないという基準が無いから

初谷
基準がないのは難しいですね。一般の方が見分けるにはどういうところを見ればよいのでしょうか?

大森さん
そうですね。例えば気密性能で言えば、数値で表す事ができます。C値っていうんですが、隙間の大きさを表しているので、数値が小さいほど隙間が無いよっていうことで、気密性能が優秀。僕たちがよくお伝えさせてもらってるのは、1.0以下ですね

初谷
C値が1.0以下かどうかを確認すればよいんですね

大森さん
そうです。欲を言うなら、0.5以下にしてあげると、びっくりするぐらい洗濯物は気持ちよく乾くし、快適性は格段に上がると思います

初谷
なるほど。すごく勉強になりました。お話をお伺いするとC値の重要さが分かりますが、知らないと建ててから後悔することになってしまうんですね
このインタビューを行った、アトリエ建築家の設計による「等身大でかっこいい家」コンセプトハウスのルームツアーは >> こちらからご覧になれます
「デザイン・性能・コスト」のバランスをとれる会社に


初谷
そういう経験を経て建房さんを創業されたと思うのですが、建房さんがやってらっしゃる家づくりで、大事にしているのはどんなことでしょうか?

大森さん
僕が住宅会社に勤めていて施主の立場を経験して感じたのが、皆さんが住宅に求める3大要素のデザイン・性能・コストを全部満たす家ってなかなか無いなってことなんです。分かりやすくいったら「めっちゃオシャレでカッコ良くてすごく性能が良くてすごく安い家」って残念ながら存在しないんですよ

初谷
すごく欲張りな3つですよね

大森さん
住宅業界を見回した時に、この3つの内の大体どこか1個尖ってるんですよ。
例えば「ウチはデザインが最高なんですが、性能はちょっとそこまでは…でも、デザイン良いからいいでしょ」という会社さんとか「ウチはデザインは得意じゃないんだけど、性能はもう抜群なんです」っていう会社さん。あと「デザインも性能もちょっと得意じゃないんですけど…安さだけはもう誇れますよ」という会社さん

初谷
確かに、分かる気がしますね

大森さん
確かに個性も大事だと思うんですが、僕がお客さんだったら「3つともこだわりたい」って思うんですよね。だからこの3つのバランスをとれる住宅を建てる会社を作ろうっていうのが、1番のコンセプトです

初谷
オシャレな家を求めると、性能が取れなくなるっていう風に思いがちですけど、決してそうじゃないということですか

大森さん
そうじゃないです。それは夢のお話だと思われるかも知れませんけど、それを夢じゃない手法を弊社は保有してるということですね

初谷
なるほど。疑ってるわけじゃないですけど、僕も今聞いて「本当にそれ出来るのかな」って思ってる部分もあります(笑)

大森さん
口で言うのは簡単なんですけどね(笑)。でも、ちゃんとロジックはあります

初谷
それは住宅業界に携わり始めた時から、徐々にそういう風に考えていったのでしょうか?

大森さん
やっぱり1番は、広くし過ぎてしまったという僕の失敗が大きかったのと、理想を追いながら、トライアンドエラーを繰り返し、今に至るっていうのが正直な所ですね
このインタビューを行った、アトリエ建築家の設計による「等身大でかっこいい家」コンセプトハウスのルームツアーは >> こちらからご覧になれます
住宅価格が決まる仕組みとは


初谷
広くなると色々コストも掛かってくるけれども、坪数を絞ったとしても、広がりを感じる家にしてしまえばコストが抑えられるから、その代わりに性能をあげるとかいうことですか

大森さん
仰る通りで、例えばロジックの一つがそれですね。今の家の価格って、色んなもちろん要素はありますけれども、何で決まってるかって言ったら、最大ウェイトを占めてるのは、大きさなんですよ。僕たちが、職人、基礎屋さんとか、大工さんとかにお仕事を依頼したときに、報酬は大きさで決まるんです

初谷
なるほど

大森さん
㎡単価が決まっているので、大きくなれば大きくなるほど、報酬は上がっていくわけです

初谷
ここでも単価は㎡数で決まるんですね

大森さん
はい。そのコストは誰が払うかっていったら、お客さんなんですよね。35坪が平均値っていわれてますけれども、30坪の家で35坪の広がりを感じれる家を建てる事ができれば、30坪のコストで35坪の満足度

初谷
そうですね。5坪分はコストを抑えれたということになりますよね

大森さん
そうです。僕のような逆パターンもあるんですよ。40坪の家で、35坪の広がりしか感じれない

初谷
それ聞くと寂しいですね

大森さん
はい。成功例と失敗例では、面積としては10坪の差がある。坪単価という表現は、僕はあんまり好きではないですが、仮に建坪60万の注文住宅があったとしたら、同じ満足度でも10坪違ったら600万違いますからね

初谷
なるほど。坪数通りの満足度っていうのは、決して悪い事じゃないかもしれないですが、もっと良いやり方があるかも知れないって事ですね

大森さん
そうです、そうです。コストパフォーマンスが高くなった分、性能とかデザインに回してあげて、満足度をよりあげる方法もあるんだということを分かってもらえたらうれしいです

初谷
なるほど。勉強になりました。ありがとうございます

大森さん
言うのは簡単なんですけれどもね。これをしようと思ったら、スキルが必要です。それは僕らが、磨いてきた財産でもありますかね
このインタビューを行った、アトリエ建築家の設計による「等身大でかっこいい家」コンセプトハウスのルームツアーは >> こちらからご覧になれます
↓次ページは「家づくりの話の前にやらなければいけないことがある!?」 ↓